

代表取締役社長
杉中 美勝
01:デジタルトランスフォーメーションの現状
VUCAの時代と言われて久しい現在、デジタル技術によってビジネス環境の変動性・不確実性は高まり、既成概念は破壊され、新たなスタンダードで上書きされていきます。
そんな外部環境に急かされるように、変わらなければならない雰囲気が醸成され、漠然と変化の必然性を認識していても、何が正解か見えずどう動けば良いのかわからない。今はそんな時代と言えるのではないでしょうか。
しかし、わからないからアクションが起こせないというのでは、状況の悪化は免れません。
弊社主催の「デジタル変革推進セミナー ~デジタルトランスフォーメーションの波を乗り越えるためには~」では、経済産業省 商務情報政策局 情報産業課 課長補佐 飛世 昌昭氏にご登壇いただき、2019年11月時点でのDX推進指標平均は1.4、目標の3.0とは乖離のある現状が述べられました。
経済産業省がDXレポートで述べた2025年の崖は、トランスフォーメーションへのマイルストーンであり、変化に躊躇する国内企業への問題提起に他なりませんが、その動きはまだ鈍いという現状認識です。
02:現場に潜む変化を阻む壁
ここで、私たちの立場や視点を少し説明します。
私たちはBPOソリューションベンダーです。多くのお客さま企業の業務処理を、ビジネス・プロセス・アウトソーシングという形で受託してきました。
つまり、数多くの業務処理の現場を経験しています。
多くの場合、私たちが業務を受託する前は、お客さま自身が業務を行っています。私たちは各社で異なるお客様独自の業務プロセスや手順を可視化し、現状の課題や今後のありたい姿をふまえ、業務プロセスや処理手順を再設計した後、毎日の業務処理を実施します。
30年近くこうしたことを繰り返してきたなかで確かに言えることは、「業務処理(事務系オペレーション)において、製造業の生産現場のようにシステム化・自動化されている現場は見たことがない」ということです。大規模な業務処理センターを除き、大多数を占める業務処理現場において、製造、金融、サービスなどの業界や規模を問わず同じことがいえます。
ERPや業務処理システムの導入によって一見標準化されているように見える業務でも、運用の仕方が不統一だったり、小さな単位で各々独自のルールが採用されていたり、EUCの過剰活用(自己流Excel等の肥大化・増殖)があったりと、時間と共に独自性が高まり属人化し、小さな変更に対応することができても、変革への対応が難しい状況に陥っているのです。
こうした環境下でデジタルトランスフォーメーションの実現に向けてトップダウンで旗を振っても、現場では個別最適化が進みすぎていて、管理職は間に挟まれ身動きが取れず、変化スピードが遅延するという状況になりかねません。

03:デジタルトランスフォーメーションを加速するために
デジタルトランスフォーメーションの対象は、新製品・サービスの開発などの新しい分野に目が向けられがちですが、こうした活動は成果創出まで時間を要するものです。他方で、現事業のビジネスモデル変革や業務効率化といった分野はゼロからイチを生み出すのではなく、今あるものを変革・改善していくため、効果が見えやすく、変革に向けた活動の勢いを加速するという意味においても有効です。
国内のDXに関する取り組み調査でも、回答企業中3割程度の企業が「業務効率化による生産性の向上」において成果創出できているという結果が出ています。
※IPA 独立行政法人 情報処理推進機構 デジタル・トランスフォーメーション推進人材の機能と役割のあり方に関する調査
では、業務効率化・生産性向上への取り組みを実現し、その先のデジタルトランスフォーメーションを加速度的に進めていくためにはどうしたら良いのでしょうか。
アプローチの方法はひとつではありませんが、まずは現在収益を上げている事業の業務プロセスや手順を正確に把握し、課題を把握して、複数の施策をトライしていくことが有効です。自動化が有効である処理にはRPAを適用することが成果への近道です。業務プロセスの問題が発見できればワークフローの改善という方法もあるでしょう。
こうしたアプローチを有効に機能させることができるのは、事前の可視化・課題認識のステップを踏んでいるからです。
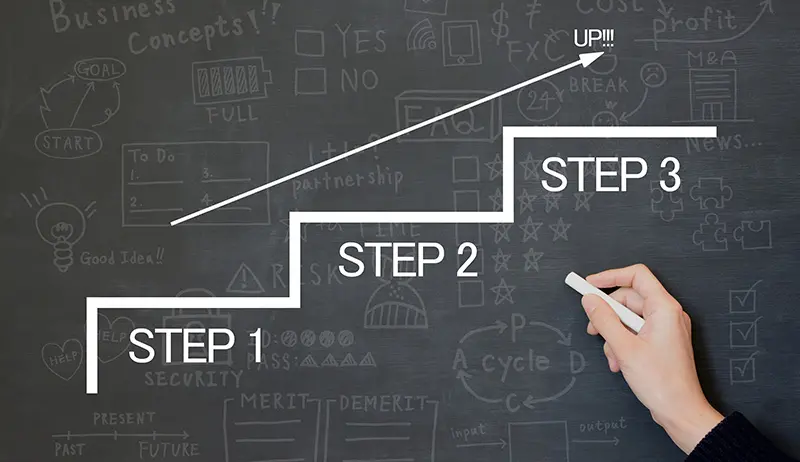
このステップを踏むことは非常に重要です。ソリューション導入を有効化することができるだけでなく、ここから先さらにデジタルトランスフォーメーションを進めていくなかで、変革の動きが現場で止まってしまうことを回避する処方箋にもなり得ます。可視化された情報に基づき、現場・管理職・トップなど多階層のステークホルダーが協議することで認識ギャップを埋めることができるのです。
私たちは、上で述べた、AS IS(現状課題)を分析し、CAN BE(部分トライ)による検証を行い、TO BE(あるべき姿)を構築するというステップで、デジタルトランスフォーメーションを進めていきたい、というお客さまの伴走支援を、ニーズにあわせて複数のサービスで展開しています。

